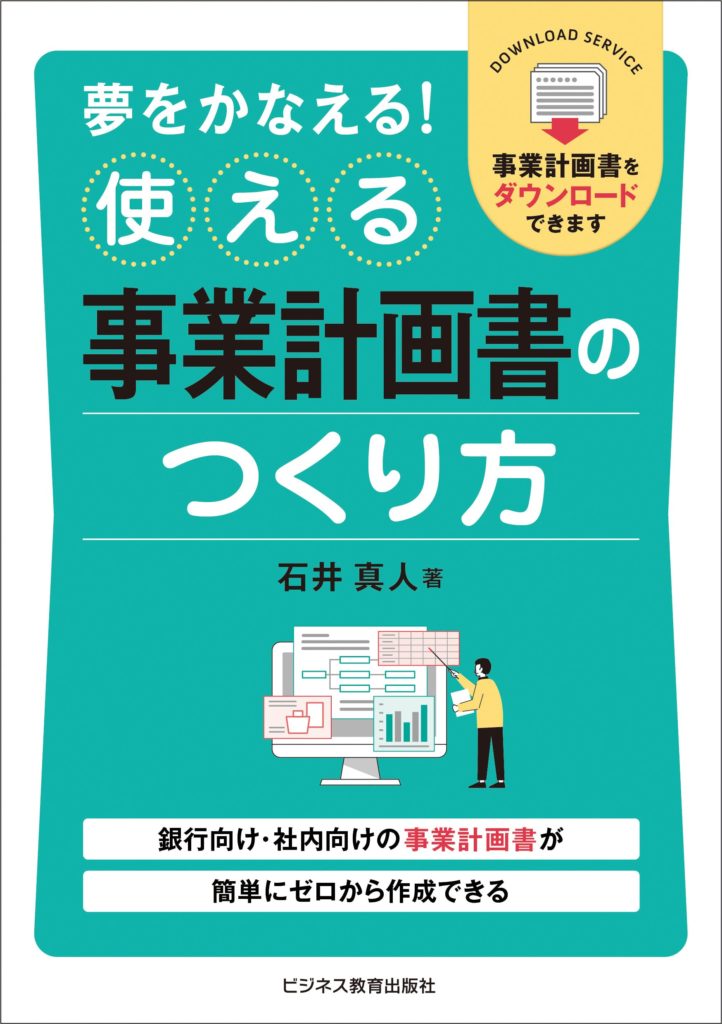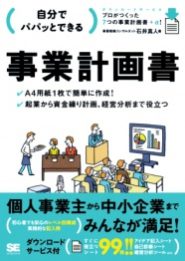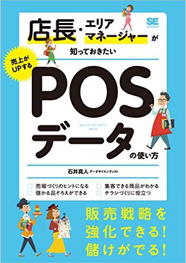「業務フローチャートによって「できること」を知るー1.業務マニュアルとして使える」で軽くふれたテーマですが、業務フローチャートは与えられた仕事の進め方がわかる「業務マニュアル」として活用できます。しかし、業務マニュアルがあっても、従業員が業務マニュアルに従わないケースは山ほどあります。今回は、この問題について説明していきたいと思います。
なぜ、業務マニュアル(業務フローチャート)は無視されるのか?
まず、よく耳にする業務マニュアル(業務フローチャート)に対する声は、下記のような内容が多いと感じています。
- 実際の業務と、マニュアルの内容が違っているので使えない
- マニュアルが間違っていても、内容が正しく変更されない
- マニュアルよりも、もっと良い方法がある
- マニュアルをゆっくり読んでいる暇がない
- いきなりマニュアル通りの仕事はできない
- マニュアルを使って仕事をするように指示されたことはない
- そもそもマニュアルがない
これらの声から考察すれば、要は、そもそも「マニュアルを使って仕事をする体制」になっていないことが根本的な問題だと言えそうです。
仮に、実際の業務と完全に合致した業務フローチャートが存在しているとしても、それをマニュアルとして使うことを会社として指示しなければ、”マニュアルを確認する”というひと手間が作業に加わります。つまり、作業負担が増えて面倒くさいから、いちいちマニュアルを見たくないのです。そのためマニュアルが実際の業務と一致してなければ、マニュアルを見ないのは当然なのです。
これは組織体制という形式がありながらも、組織単位で仕事の品質を高めていく運営がなされていないからであり、個人の技量に頼って仕事の品質を高めていく日本的なレガシーが根付いているからだと思います。
組織単位で成長するよりも、個人の成長に頼った方が、より早く成果を得やすい印象はあります。個人の場合、優秀な人材を見つけてフル活用すれば、必然的に実践から学ぶ機会が特定の人物に集中するため成長スピードも速くなります。一方、組織単位の場合は、標準化された業務の品質を少しずつ向上させていく必要があるため、成長スピードは遅くなります。
しかし、特定の人物だけに仕事が集中し過ぎると、疲弊して存分に働けなくなったり、もし退職したりすれば大幅な戦力ダウンとなります。つまり、個人の技量だけに頼っていると、なかなか組織体制が安定しないのです。一方、組織単位で標準化された業務が確立されていると、人材の入れ替えがあっても仕事の品質は保たれるため戦力ダウンを抑制できます。言うまでもなく”標準化された業務”とは、業務マニュアル(業務フローチャート)のことです。
以上のように組織と個人で対比しましたが、要は個人の技量に頼るという組織風土があるため、会社として「マニュアルを使って仕事をする体制」を重視しないのであり、結果としてマニュアル(業務フローチャート)を作成しても誰も使わないのだと思います。
業務マニュアル(業務フローチャート)を使って仕事をする体制のポイント
最後に、ご参考までに業務マニュアル(業務フローチャート)の運用を重視する時に必要なポイントを挙げておきます。
- マニュアル通りの業務遂行を徹底する
- 各工程における作業時間を計測する
- マニュアル通りに業務遂行した結果、問題が生じれば、不備な点を実務者に報告してもらう
- 業務遂行の結果、問題が生じても個人の責任を追及しない
- 報告された不備は必ず検証する
- 検証の結果、改善が必要であれば”マニュアルから修正”する
- 改善されたマニュアル通りの業務遂行を徹底する
- 業務マニュアル(業務フローチャート)の運用担当者を決めておく
個人の技量に頼った体制になっている会社の人達からすると、違和感を感じるプロセスかもしれません。しかし、仮に非効率なマニュアルであっても、その通りに仕事をしてもらうことが大切です。そうしなければ、マニュアル上の問題点はいつまで経っても洗い出されないし、従業員がマニュアルを信じることは永遠にありません。「マニュアル通りに業務を遂行すれば、問題なく仕事が終わる」という実体験を全従業員で積み重ねていく必要があるのです。
その上で、いくつか注釈を加えておくと「作業時間の計測」は、個人ごとの効率性を確認するためです。もし、作業時間にバラつきがあるのであれば、その工程内における作業手順に属人的に左右される要素が隠れているとわかります。
また、マニュアルに従って問題が生じた場合に、個人の責任を追及しないことも大切です。マニュアル通りに業務を遂行した結果、問題が生じたのであれば、責任はマニュアルにあるのです。これを無視して個人の責任を追及すれば、マニュアル通りの業務遂行に対して消極的な姿勢になるのは必然です。
そして、問題が生じれば、その原因を業務マニュアル(業務フローチャート)を分析して抽出することが大切であり、業務改善する場合はマニュアルを改定した上で、その新しいマニュアルに従って再び業務遂行を徹底することで検証しなければなりません。そうでなければ、改善したマニュアルの正しさが保証できなくなります。
最後に、業務マニュアル(業務フローチャート)の運用担当者を決めておくことです。実務担当者が、自分が与えられた主たる業務を抱えながら業務マニュアルを管理することは、時間的にも、精神的にも相当に負担が大きいものです。これでは、いずれマニュアルが形骸化し、実際の業務から乖離して使ってもらえなくなります。そのため、独立したマニュアル運用担当者を設置することが理想であり、それが無理な場合は、少なくとも各組織単位の管理職に担当してもらった方が良いと思います。
ここでは要点だけ書きましたが、上記の手順を自社に適合させて運用できれば、安定感のある組織体制構築に向かっていくはずです。属人的な体制からの脱却を検討されているならば、ぜひ参考にして頂ければ幸いです。